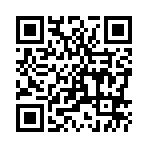2019年01月03日
波田地区の三九郎
波田地区では、今は1月第2週の土曜か日曜(今年は1月12日か13日)に行う地区が多くなっています。
波田地区子ども会育成会発行の三九郎に関して詳しい記事がありますので、以下転載します。
三九郎は全国的に「どんど焼き」といいます。
波田では1月第2週の土曜か日曜に行う地区が多くなっていますが、本来のどんど焼きは小正月(1月15日)に、正月の松飾り・注連縄・書初めなどを燃やす、お正月の火祭り行事です。
やぐらの作り方もいろいろあります。
右の写真は北九州で、右が横浜です。 注)写真は省略
どんど焼きの由来は平安時代にさかのぼります。
平安時代、貴族のホッケーに似た遊びがありました。
この遊びで、「毬杖(ぎっちょう)」という杖が使われていたのですが、京都の宮中の庭で正月の15日に、この毬杖を三本立て、扇などを結び付け吉書を添えて焼く行事が行われたそうです。
この行事が民間に伝わって、今のどんど焼きになったと言われています。
本来の三九郎のやぐらは三本足のようです。
三九郎の呼び名は松本・塩尻と周辺の旧松本藩だけの呼び名で、県内ではホンヤリ・オンベ・ドーロクジン・ドンドヤキ・サンチョなど30種類以上の呼び名があります。
この火にあたると丈夫になる。団子を焼いて食べると風邪をひかない。書初めをかざして高く舞い上がると書が上達する、と言われています。
以上、転載終わり
波田地区子ども会育成会発行の三九郎に関して詳しい記事がありますので、以下転載します。
三九郎は全国的に「どんど焼き」といいます。
波田では1月第2週の土曜か日曜に行う地区が多くなっていますが、本来のどんど焼きは小正月(1月15日)に、正月の松飾り・注連縄・書初めなどを燃やす、お正月の火祭り行事です。
やぐらの作り方もいろいろあります。
右の写真は北九州で、右が横浜です。 注)写真は省略
どんど焼きの由来は平安時代にさかのぼります。
平安時代、貴族のホッケーに似た遊びがありました。
この遊びで、「毬杖(ぎっちょう)」という杖が使われていたのですが、京都の宮中の庭で正月の15日に、この毬杖を三本立て、扇などを結び付け吉書を添えて焼く行事が行われたそうです。
この行事が民間に伝わって、今のどんど焼きになったと言われています。
本来の三九郎のやぐらは三本足のようです。
三九郎の呼び名は松本・塩尻と周辺の旧松本藩だけの呼び名で、県内ではホンヤリ・オンベ・ドーロクジン・ドンドヤキ・サンチョなど30種類以上の呼び名があります。
この火にあたると丈夫になる。団子を焼いて食べると風邪をひかない。書初めをかざして高く舞い上がると書が上達する、と言われています。
以上、転載終わり